anchor
余ったハードディスクを結合して大容量ストレージを実現する〜Macのディスクユーティリティを使ってJBOD機能でボリューム結合する

2009年モデルのMacBook Proと2015年モデルのRetina MacBook Pro、最近導入した2019年モデルのMacBook Pro、先代ファイルサーバーだったMac mini、旧メールサーバー兼VPNサーバーとして使っていたMac miniなど歴代のMacにそれぞれいざという時のためのTime Machineの外付けハードディスクを着けているので、家中外付けハードディスクだらけになっている。
そのファイルサーバー用途のMacなどは内蔵ディスクを大きいものに交換したりしているので、Time Machine用のハードディスクも順次容量が大きいものに交換している。
するとかつてバックアップ用だった1TB程度のハードディスクなんかは容量が中途半端で使い道がなくなってくる。
かといってさすがに1TBの容量があるストレージなので捨てたり、埃をかぶらせているのももったいない。
ならば余った大容量ハードディスクを有効活用するためにボリューム結合で簡易的に大容量ストレージを作ってしばらく前から運用している。

我が家の「サーバールーム」の様子
AppleTV用のBluetoothリモコンサーバー兼スパムメール
フィルターサーバーやファイルサーバーなどが並んでいる
業務用ではないのでかつてのラップトップやデスクトップを転用している

大容量ストレージを構築しているのがMacBook Pro2009モデル
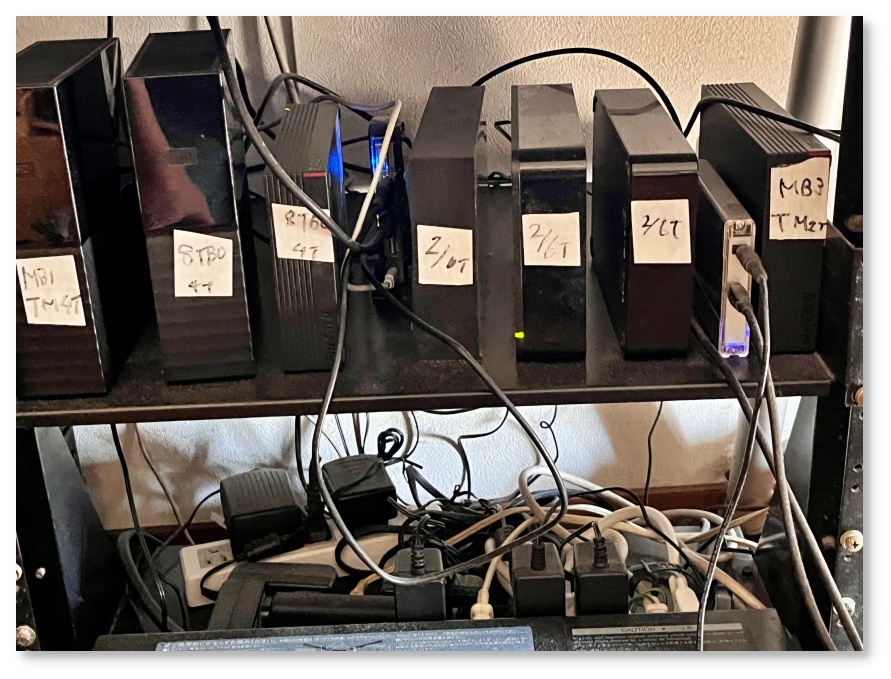
USBハズなどを介して外付けハードディスクを大量にぶら下げている
転送速度は重視していない…容量を稼ぐことが優先
余った1〜2TBのハードディスクを結合して大きな論理ドライブを構築している

これのやり方はとても簡単
ディスクユーティリティを起動して
ファイルメニューからRAIDアシスタントを選択する

現在のmacOS 15 Sequoiaで使用できるのはRAID 0のストライピング
RAID 1のミラーリング、そして連結のJBODの3つのメニュー
大容量ディスクを作るにはJBODを選択する
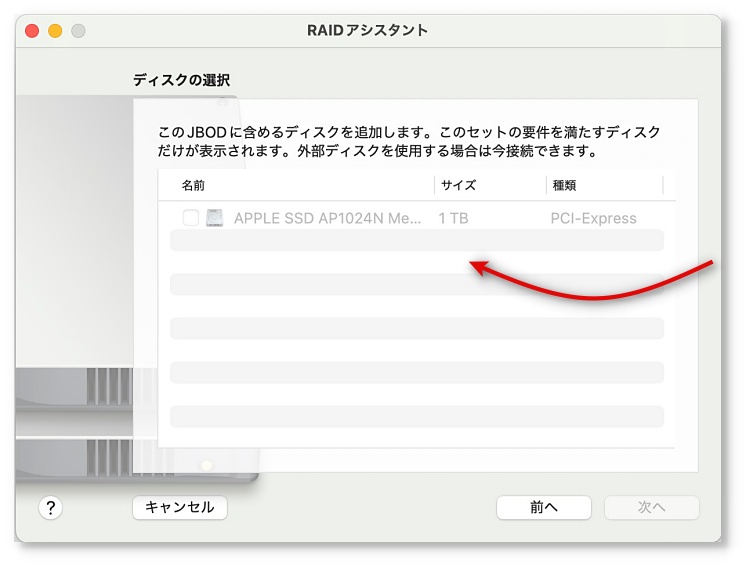
ディスクの選択画面でグループングしたいドライブのボリュームアイコンを
ドロップしてアシスタントの指示にしたがて結合操作を進める

物理的な結線を図式化するとこんな感じ
MacBook Proのアクセスソケットは数が限られるので
ハブを通して複数のハードディスクを接続する
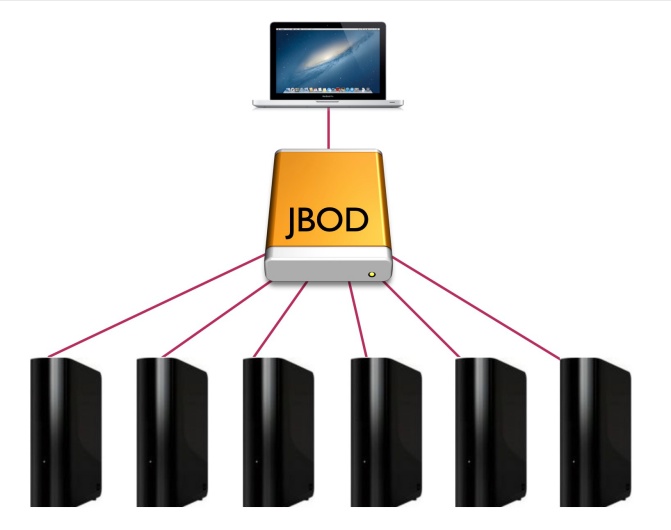
論理ドライブを図式化するとこんな感じ
例えば1TBディスクを6本まとめるとMacからは
6TBの論理ボリュームとして認識される
6TBのラックマウントNASを購入するより二桁ぐらい安上がり
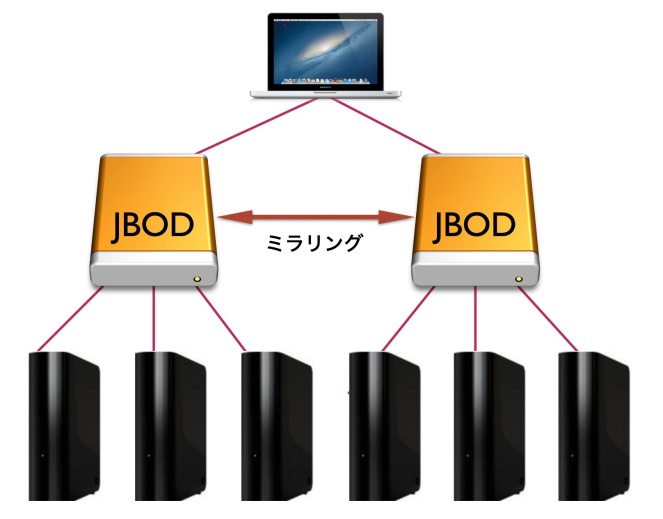
ただしJBODには問題点がある
JBODは単純に複数のドライブの最後尾と先端を続きとして結合するだけなので
ディスクを2つ結合すれば故障リスクは2倍、3つ結合すればリスクは3倍
6個繋げばざっと6倍となって平均的なHDDの寿命が6年とすると
この組み合わせは1年以内には何らかの故障を起こすことになる
そこでJBODボリュームを2セット構築してこの2セット間を
rsyncコマンドなどでミラリングすれば片方が故障しても
修理をしている間もう一つのセットがデータを保持できる
完全リダンダントの考え方があれば堅牢な大容量ストレージが
とても安価に実現できる
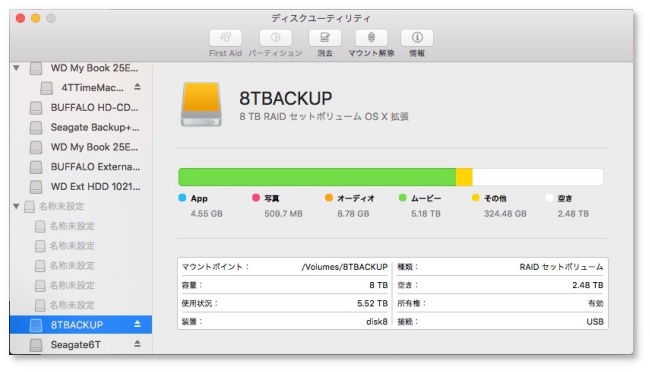
この複数ボリュームを結合するJBOD機能は確かLeopardあたりから
MacOSに追加されたが一時期ディスクユーティリティのメニューから外されていた
最近のバージョンSequoiaかそのあたりからまた復活している
El CapitanのMacBook Proでは論理ボリュームは認識できるが
構築するRAIDアシスタントがないため構築や変更ができなかった

この機能とはまた別だがSonomaで確認したらMacのボリュームは
コンテナ化されており複数のボリュームの構築も可能になっている
macOSの場合セキュリティ強化の狙いでコンテナ化されているようだが
これが使えるなら以前のBootCampよりもさらに堅牢な仮想環境が構築できるかもしれない
いろいろ面白いことができそうな機能
Previous
Index
Next

|